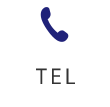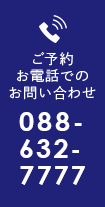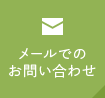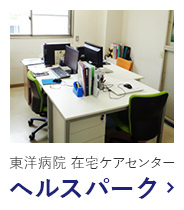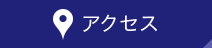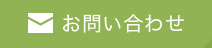2024.03.13
【コラム】薬剤部より~漢方彩々 2024年 春号~
先日の第2回膠原病・リウマチ教室にご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。この度は薬剤課職員も皆さまの前で講演させていただいたほか、当院の漢方啓発部門(※非公認部署です)としてオリジナルのお茶の提供等お手伝…続きを読む2023.07.24
【コラム】薬剤部より~漢方彩々 2023年 夏号~
梅雨が明けて本格的な夏の到来も間近というところ、漢方薬や生薬を扱う上で避けては通れないこの季節特有の重大問題をご存じでしょうか。かの有名な仁寿会三大随筆のひとつ『東洋草子 第一段』にも以下のような記述が残されています。…続きを読む2022.05.09
【コラム】薬剤部より~漢方彩々 2022年 立夏~
桜が散って道路脇のツツジもそろそろ見頃を過ぎ、緑萌ゆる季節となりました。皆さま今年のゴールデンウィークは久しぶりに羽を伸ばすことができたでしょうか。最長で10連休になる最終日の5月8日は「母の日」が重なるということで、…続きを読む2021.09.28
【コラム】薬剤部より~漢方彩々 2021年 夏秋号~
リモート会議、オンライン飲み会、テレワーク――離れた場所で気軽に顔を見ながら会話が可能になり、最近は患者様への面会もリモートで行わせていただくようになっています。そんなオンライン化の波が押し寄せる中、本年6月には当院に…続きを読む2021.03.19
【コラム】薬剤部より~漢方彩々 2021年 春号~
暖かな陽気に桜の開花も進み、春の気配がそこかしこに感じられるようになりました。厳しい冬を乗り越え陽春に手が届いた方も、まだ少し風の冷たさに震えておられる方も、さまざまな想いを抱えてこの春を迎えられることと思います。 …続きを読む2020.12.01