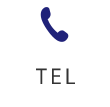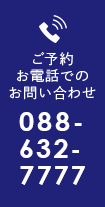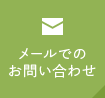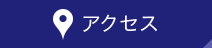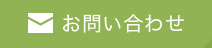やさしい味付けと彩りのバランスが、目にも心にも食欲を運んでくれます。病院食というと「味気ない」という印象を持たれがちですが、この献立は家庭的な温かみと栄養バランスの両方が整った一食です。
このお食事は隣接するサービス付き高齢者向け住宅、ショートステイやデイケアでも提供されています。入院中の方だけでなく、在宅生活を送る高齢者や通所利用者様も、同じ美味しさと健康サポートを受けられるのです。

ひと口ごとに、元気をくれる今日の献立
本日の昼食は、白ご飯、ビーフシチュー、スパゲッティサラダ、そしてデザートにシャインマスカット。飲み物は冷たい麦茶です。色彩も鮮やかで、見た目からも食欲をそそります。
栄養のちからで、夏を乗り切る
- ご飯:主食としてエネルギー源を確保し、脳や筋肉の働きを支えます。
- ビーフシチュー:牛肉の良質なたんぱく質と鉄分が含まれ、鉄分補給により、貧血予防の助けとなります。さらに、やわらかく煮込まれたにんじん、スナップエンドウ、マッシュルームが彩りを添え、ビタミンをバランスよく補ってくれます。
- スパゲッティサラダ:炭水化物に加え、マヨネーズの油分がエネルギー補給に。彩り野菜で食物繊維も補えます。
- シャインマスカット:ブドウ糖がすばやくエネルギー補給し、ビタミンCも含み糖質やビタミンCの補給により、疲労回復を助けます。
いつまでも自分らしく歩くために 〜フレイルというサイン〜
年齢を重ねると、体も心も少しずつ変化していきます。 「最近歩くのがゆっくりになった」「外に出るのがおっくうになった」「なんとなく疲れやすい」―― そんな小さな変化は、もしかするとフレイルというサインかもしれません。
フレイルは、元気な状態と介護が必要な状態のちょうど間にある「虚弱期」のこと。 筋力や持久力が少しずつ落ち、体重や活動量が減っていくことで、日常生活の元気が失われやすくなります。 日本では、65歳以上の方の約1割がフレイル、4割が予備軍といわれています。
でも、これは「老化だから仕方ない」という話ではありません。 フレイルは、早く気づいて対策すれば元の元気な状態に戻ることもできる、可逆的な状態なのです。
そのために大切なのが、
- ・栄養のある食事をきちんと食べること
- ・体を動かし、筋肉と骨を守ること
- ・人と関わり、心のハリを保つこと
たとえば今日の昼食のビーフシチューは、たんぱく質と鉄分が豊富で、筋力と血の巡りを支えてくれる心強い一皿。 こんな一食一食の積み重ねが、明日の元気と、未来の「自分らしい暮らし」につながります。
フレイルのサインは、体がくれる優しい合図です。
フレイル予防としての意義
高齢者に多い「フレイル(虚弱)」は、筋力や持久力、体重、活動量の低下が重なって要介護状態へ進む前段階です。 その予防には、たんぱく質とエネルギーのしっかりした摂取が欠かせません。 牛肉は良質なたんぱく質と鉄分を豊富に含み、筋肉や骨の健康を支えるだけでなく、貧血予防にも役立ちます。 特にビーフシチューのような温かい料理は消化を助け、栄養を効率よく吸収できるため、食欲の落ちやすい方にも適しています。
東洋医学でひもとく、体にやさしい理由
東洋医学では、牛肉は「脾胃を補い、気血を養う」食材とされます。特に疲れやすい方、血色が悪い方に適しています。シチューの温かさは「脾」を温め、消化機能を高める作用も期待できます。 また、マッシュルームや野菜は「清熱・潤燥」の働きがあり、夏場の熱や乾燥から体を守ります。シャインマスカットは「補気生津」といい、体力を回復し喉の渇きを潤す果物です。暑い季節にぴったりです。
薬膳の小さなお話
薬膳の考え方では、「甘味」は気を補う働きがあり、心身の安定と満足感、疲労回復を助けます。ご飯、にんじん、マスカットなど自然の甘味は、心地よい満足感を与えると同時に疲労回復にもつながります。さらに、温かい料理と冷たい果物の組み合わせは「陰陽のバランス」を意識した薬膳的な知恵です。
栄養士さんからの“ごほうび”
今日は栄養士さんが特に気合を入れてくださったそうで、大粒で甘みの強いシャインマスカットが添えられていました。食後の楽しみとして、口の中に爽やかな甘味と香りが広がります。
牛肉の「温かい性質」は、体だけでなく意志力や行動力の波動を高めると考えられます。
大地で育った動物のエネルギーを取り込むことは、「地に足をつける」感覚を強め、精神面でも安定感を与えます。
特にビーフシチューのように長時間煮込まれた料理は、火のエネルギーで柔らかくなり、「心をほぐす温もり」を届けてくれます。
暑い日が続きますが、素敵な食事に心がけて健康でいてください。
【注釈】
各個人様にお出しするお食事は、体の状態や医師の指示により内容が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の診断・治療に代わるものではありません。症状や治療については必ず主治医にご相談ください。