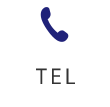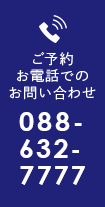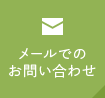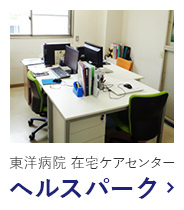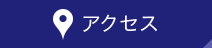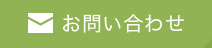2024.10.11
第3回 東洋病院市民公開講座 『膠原病・リウマチと歩む健やかライフ』開催
2024年10月6日(日)大勢の東洋病院スタッフがチームとして準備と開催に関わりました 受付嬢 司会はリハビリ室の澤内さん 清水理事長…続きを読む2024.09.20
あなたにとっての秋の味覚は何ですか?
太郎「美味しそうなブドウだね」 花子「すごく上手く描けてるわね」 太郎「塗り絵は僕も大好きだよ」 花子「塗り絵は脳の活性化や手指のリハビリに繋がるのよ」 太郎「きちんとリハビリとしての意味があるんだね」…続きを読む2024.07.04
「通所リハビリ」からのお知らせ♪
6月の「みんなで☆作業療法♪」の紹介です(*^▽^*)ノ 梅雨も自然のはからいですね(^^)晴れた日が続くといいですね☆ 利用者「紙に染めた色が紫陽花になるとは、ビックリしました(・□・)!」 「いっぱい作…続きを読む2024.07.03
楽しいことがいっぱい(千寿園)
こんにちは!ちい川☆です。 暑さに加えて雨で疲れる季節ですね_( _´ω`)_ペショ 我が家の子どもたちはプールに泥遊びと毎日夏を満喫し、 肌を小麦色に染めております。(家の中でまでゴーグルつけてるのはやめてほし…続きを読む2024.07.01
「通所リハビリ」からのお知らせ
7月のカレンダーを紹介いたします(^^)/☆ 新たな取り組みに「CINEMA」を加えました。「笑い」「感動」「驚き」を皆様と共有できる時間を目指して参ります(*^▽^*) …続きを読む2024.06.30
「通所リハビリ」からのお知らせ
梅雨の「ジメジメ・イヤイヤ(>‗<)/~」な時期を、さわやかな色彩と遊び心でお迎えしております♪ まだまだ、続く梅雨時期ですが、デイケアの玄関は雨雲の隙間から晴間がのぞいているかもしれませんね☆彡…続きを読む2024.05.31
実習医学生ミニ演奏会♬
2024年5月30日 2週間の地域医療実習で東洋病院を訪問している徳島大学医学科6年生の男子医学生が病棟でバイオリン演奏会を開催してくれました。 当院入院中の患者さんや職員が聴衆として参加し、そ…続きを読む2024.05.14
●-RA(14) 関節破壊をくいとめるために
関節リウマチはあちこちの関節に滑膜炎という炎症をきたし、関節の腫れ(上図左)と痛みを生じる大変つらい病気です さらに怖いのは、数年から十数年が過ぎると、滑膜炎が軟骨・骨破壊を引き起こすことです …続きを読む2024.05.10
「通所リハビリ」からのお知らせ
作業療法作品をご紹介☆(^0^)☆ 5月といえば、「鯉のぼり・藤の花」でっかく掲示中! ⇒ 始めは紙を切って・・・ ⇒⇒ 1つ1つ丁寧に・・・ ⇒⇒⇒<藤の花>…続きを読む2024.05.04
「通所リハ」からのお知らせ
皆様をお出迎えするデイケアのエントランスを紹介いたします(^▽^)/ 来所時は是非お顔を上げていただき、季節の花に囲まれながら優雅に泳ぐ鯉のぼりをご覧ください♪ (利用者様とスタッフで手掛けた作品は、来所された皆様…続きを読む2024.04.24
デイケアより☆5月のカレンダー紹介☆
デイケアです。5月のカレンダーを紹介いたします☆ いい汗かいて(^^☆)みんなで楽しく過ごせる時期が来ましたね♪ 5月の作業療法作品は・・・カレンダーにヒント♪ 完成したら、お知らせ致します(^O^)‼ &nb…続きを読む2024.04.22
はるの風が~吹いてきたら~♪(千寿園)
メダカも ちょうちょも ことりたちも~♪ うれしそうに~♪ わらうだろう~♪ 春だよ♪ぼくらの♪はるがきたよ~♪ こんにちは(^^♪ちい川☆です。素敵な春がやってきましたね! 新学期を迎えた子…続きを読む2024.04.15
医学生、実習奮闘中 (^^♪
徳島大学の医学科6年生(向かって右端)が先週から当院で実習中です☆ 数ある地域医療機関から、実習病院として東洋病院を選択してくれました。 今日の午後はリハビリ室で当院のPT・OT達に指導を…続きを読む2024.04.11
●-RA(13) 関節外病変(その2) 間質性肺炎
間質性肺炎は、肺の間質という肺胞の壁の部分に炎症が起きる病気です。 関節リウマチ患者の10-30%に発症するとされており、労作時息切れ(息苦しさ)が自覚症状としてみられます。 間質性肺炎の診断には…続きを読む2024.04.09
**I know I’m happy…**
Nothing is forever in this world この世界では永遠なんてものはないけれど But don't be sad 悲しまないで The spring is just around the…続きを読む2024.03.28
●-RA(12) 関節外病変(その1) リウマチ結節(リウマトイド結節)
関節リウマチは主に関節を侵す病気ですが、関節以外にも病変がみられることがあります。 リウマチ結節(リウマトイド結節)はその関節外病変の代表的なものとして知られています。 リウマチ結節は関節リウマチ…続きを読む2024.03.27
**「ありがとう。」**
やさしく澄んだ春の空。 どんなときも、相手をおもいやり、そして「ありがとう。」と あたたかい手と、あたたかいまなざしで、つたえてくれる、あの人のように、 やさしく澄んだ空です。 「ありがとう。…続きを読む2024.03.21
一日ってどんな感じ?【千寿園】
こんにちわ!ブログ担当の☆ちい川☆です! いきなりですが皆様はグループホーム(以下【ホーム】と省略)という場所にイメージはあるでしょうか? 介護施設も色々ありますがそれぞれに違いがあります。 今回はホームでの一日の…続きを読む2024.03.21
ブログはじめました。【千寿園】
こんにちわ。ようやく寒い季節が終わりそうですね。 この度グループホーム千寿園では日々の様子や情報を皆様にお伝えできればと思い、 ブログを始めることにいたしました。 パンフレットや説明だけでは伝えきれない部分にフォー…続きを読む2024.03.18
●-RA(11) 2種類あるリウマチの痛み
関節リウマチの関節の痛みには、その原因によって大きく2つの種類があることをご存じでしょうか? 上の図をご覧ください。この図は発病した一人の関節リウマチ患者さんを治療せずにその痛みの経過を追った図です。 …続きを読む2024.03.13
●-RA(10) 関節破壊の進行について
関節リウマチ(RA)では関節の炎症が関節の破壊を引き起こします。 見かけ上の関節の変形が発症10年過ぎてからみられることから、左図のように関節の破壊は10年過ぎてから進行していくと従来の予測(左図青線)…続きを読む2024.03.13
【コラム】薬剤部より~漢方彩々 2024年 春号~
先日の第2回膠原病・リウマチ教室にご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。この度は薬剤課職員も皆さまの前で講演させていただいたほか、当院の漢方啓発部門(※非公認部署です)としてオリジナルのお茶の提供等お手伝…続きを読む2024.03.11
**願いがひとつ、叶った日。**
先日、「リウマチ相談員一年生」として、 リウマチ・膠原病教室に参加してきました。 「リウマチカフェ」、やりたいな。 東洋病院で働き始めてすぐに、患者さんや優しい職員さんたちと 関わる中でできた夢のひとつで…続きを読む2024.03.10
◎。.第2回 膠原病・リウマチ教室.。◎
2024年3月10日、第2回 膠原病・リウマチ教室を開催いたしました。 今回は、膠原病・リウマチ患者さんととても関係の深い、「骨粗しょう症と治療薬~正しく知って骨折予防!~」の講演と、 昨年実…続きを読む2024.03.08
●-RA(9) 関節MRI検査の威力
関節MRI検査は、関節リウマチの早期診断に用いられます。 関節の診察や血液検査で、関節リウマチが疑わしいが確定診断に至らない症例があります。 発症して早期の関節リウマチは単純X線(上図右)では異常…続きを読む2024.03.05
●ーRA(8) 関節の中を覗いてみよう!
正常な関節(左図) 関節では骨と骨が向かい合って接しています。 骨の先端には軟骨という軟らかい骨がありクッションの働きをしています。 軟骨と軟骨の間には少量の関節液があり、関節がスム…続きを読む2024.03.01
●ーRA(7) これが変形性関節症だ! 関節リウマチとのチガイ
関節の痛みや腫れを訴える患者さんをみたときは、関節リウマチ(RA)以外に●-RA(3)の表に示した病気を考える必要があります。 特にその中で頻度の高い病気が変形性関節症(OA)です。 変形性関…続きを読む2024.02.28
―――あなたの”想い”で、サクラ咲く。-1-
みなさんの、”想い”で、桜を咲かせませんか? 本日、東洋病院の受付に、『サクラのポスト』を設置いたしました。 みなさんの想いを、お寄せください。 自分以外の誰かのためを想い、…続きを読む2024.02.27
●-RA(6) 関節リウマチの治療【3】
関節リウマチの治療薬としてJAK阻害剤が登場して10年(2024年2月現在)が過ぎ、現在5種類の製剤が使用可能です。関節リウマチの症状の改善や活動性の抑制に対する高い臨床効果は既に証明されており、いまや前述の…続きを読む2024.02.24
●-RA(5) 関節リウマチの治療【2】
2003年に点滴製剤として初めて生物学的製剤(bDMARDs)が登場したときは、その劇的な関節炎に対する効果に驚愕したものでした。 その後年々治療薬の種類は増加し、2024年2月現在は左図のようになっており、皮下注射…続きを読む2024.02.21
●ーRA(4) 関節リウマチの治療【1】
・関節リウマチの診断確定後には、まずメトトレキサート(MTX)の投与を考えます。・年齢や腎機能の問題でMTX以外の抗リウマチ薬(csDMARDs)が選択されることもあります。・MTXの効果が不十分な場合は生物…続きを読む2024.02.17
●ーRA(3) 関節リウマチの診断
関節リウマチの診断について 関節リウマチは、患者さんに上の写真のようにひとつ以上の関節の腫れ(腫脹)がみられれば、その可能性があるということになります。さらに、腫れた関節(腫脹関節)と圧迫…続きを読む2024.02.15
●-RA(2) 東洋病院リウマチ専門医の紹介
東洋病院の日本リウマチ学会認定の4名のリウマチ専門医を紹介します 専門医資格医師名外来診察日リウマチ専門医清水 輝記水、木、金、土リウマチ専門医三宅 恵子月、火リウマチ専門医杉田 明美金リウマチ専門医…続きを読む2024.02.14
**たいせつなひとへ。**
たいせつなだれかへの想いを、言葉にして届けられていますか? ご入院中の患者さまは、思い通りに動けなかったり、上手に話せなかったり、難病や進行性の病との闘いで つらい、くるしい・・・しんどい、諦めてしま…続きを読む2024.02.12
●-RA(1) 目指せ、寛解!
関節リウマチという病気は治療が遅れたり薬が十分効かないと関節が破壊され、日常生活に影響を及ぼす病気です。ただ、早期に有効な治療薬を投与することでその進行を抑制し、関節リウマチを完全に抑制し進行しない状態(寛解状態)に…続きを読む2023.09.16
◎。.膠原病・リウマチ教室.。◎
2023年 9月 10日 (日) 『 ◎。.膠原病・リウマチ教室.。◎ 』が開催されました。 外来患者さまとそのご家族さま へ わたしたち東洋病院のスタッフがチームとして出来ることは何か・・・? …続きを読む2023.08.28
ともに!地域を健やかに!VOL.7
ともに!地域を健やかに! 地域の医療機関へのご挨拶に伺っております。 ******************************************** 2023/7/4 連携医療機関⑫ 東徳島医療センター …続きを読む2023.07.24
【コラム】薬剤部より~漢方彩々 2023年 夏号~
梅雨が明けて本格的な夏の到来も間近というところ、漢方薬や生薬を扱う上で避けては通れないこの季節特有の重大問題をご存じでしょうか。かの有名な仁寿会三大随筆のひとつ『東洋草子 第一段』にも以下のような記述が残されています。…続きを読む2023.01.14
【ブランディング部・活動報告】支えになりたい!
仁寿会ブランディング部です。 医療法人仁寿会には、スタッフが約120名在籍しています。 長引くコロナ禍に…、疲労困憊。 …むしろ若干の諦めも感じながら…、 毎日、ひたむきに、医療・介護に従事するス…続きを読む2023.01.07
**まずは、わたしたちから。**
あたらしい1年がスタートしました。 『今年もよろしくね。』とスタッフ同士で声をかけます。 『今年もがんばろうね。どうぞよろしく。でもぼちぼちね。』といたわりあったり。 『わぁ!きれいなお花!』とドクターたち…続きを読む2022.10.04
**【やりがい】をもつこと**
一「おしえてほしい。」と困った顔。 一「このことばで合ってる?たいせつな人がひどく悲しんでる。これでだいじょうぶ?」と、LINEの文面を見せてくれました。 簡単なことばが、いくつかならべられていた…続きを読む2022.05.09
【コラム】薬剤部より~漢方彩々 2022年 立夏~
桜が散って道路脇のツツジもそろそろ見頃を過ぎ、緑萌ゆる季節となりました。皆さま今年のゴールデンウィークは久しぶりに羽を伸ばすことができたでしょうか。最長で10連休になる最終日の5月8日は「母の日」が重なるということで、…続きを読む2022.01.19
ブランディング×SDGs ~ブランディング活動報告vol.1~
2019年11月、J-SRブランディング部 として誕生した活動が、 2021年11月、【仁寿会ブランディング部】にリニューアルしました。 当時の「J-SR」は、「仁寿会-SocialResponsibilit…続きを読む2022.01.19
【おめでとうございます】
【放射線技師・藤本 博之 さん】 令和3年度秋の瑞宝章に、当院に勤務する藤本さんが選ばれました。 多くの専門職が働く病院の中で、 「放射線技師」の業務は、 診断や治療の基盤をつくる重要な役割を担っています。 …続きを読む2021.10.12
**「気づき」の重要性**
気づき、を大切にしましょう。 落ちているちいさなゴミに、気づけるか。 ゴミに気づき、 患者さんが気持ちよく過ごせるように、 自分以外のスタッフが拾わなくてもいいように、 と考…続きを読む2021.09.28
【コラム】薬剤部より~漢方彩々 2021年 夏秋号~
リモート会議、オンライン飲み会、テレワーク――離れた場所で気軽に顔を見ながら会話が可能になり、最近は患者様への面会もリモートで行わせていただくようになっています。そんなオンライン化の波が押し寄せる中、本年6月には当院に…続きを読む2021.09.21
尊敬するみなさんへ。
東洋病院 通所リハビリテーション での 「敬老会」の様子です。 たくさんの制限のある中ですが、 スタッフがアイデアを出しあいました。 美味しくて豪華な食事に。 本格的な阿波踊り(有名連に所属するスタ…続きを読む2021.08.13
**勇気のバトン**
とてもかっこいいタイトルしてしまったけれど、 そんなにかっこいいことではなくて、 医療従事者にとって、むしろ当たり前のことかもしれません。 どんなことでも、 何かにとりかかろう、とするとき 勇気が必要だ…続きを読む2021.08.02
鍼灸コラム『汗の話』
8月になり暑さも一層厳しくなっておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか。 今年は東京オリンピックが開催され、手に汗握る戦いが続いています。 &nb…続きを読む2021.07.26
**志を同じくする**
志を貫き 向上心を燃やしつづけ 夢は大きく 心は広く 想いは深く。 気持ちはまあるく、 歩んでください。 常に、「人」を想い、 その人の、よりよい未来を想像し、 自…続きを読む2021.07.02
**その人らしさ、とは**
ある患者さまの退院前カンファレンスでの出来事です。 「水の入った器を、持っていただいて、歩行する訓練もしています。 こぼさず上手に、安全に、運べます。」 担当の作業療法士さんからの報告でした。 …続きを読む2021.06.28
【電子カルテシステムを導入いたしました】
令和3年6月22日より、電子カルテシステムを導入いたしました。 地域のみなさまに寄り添った、あたたかく、きめ細やかな 診療体制の拡充を目指しております。 — みなさまの健康と安心を支える『かかりつけ医』として、 …続きを読む2021.06.18
**いちばん近くに**
病気やけがをして… 認知症が進行して… 癌が体中をむしばんで… 歩くことができない。 食べることができない。 トイレに行くことができない。 想いを相手に上手く伝えることができない。 できないこと…続きを読む2021.05.31
**支えとなるもの**
ある患者様がおっしゃいます。 「娘が待ってるから、歩けるようになって、家に帰ります。」 ある患者様のご家族がおっしゃいます。 「お母さんが生きていてくれる、それだけで、私もがんばろうとおもえるんです。」 …続きを読む2021.05.11
**essential worker**
エッセンシャル ワーカー ソーシャルディスタンス…テレワーク…ニューノーマル… コロナ禍の世の中に、たくさんの、あたらしい言葉が聞こえてきます。 【エッセンシャルワーカー】も、そのひとつです。 …続きを読む2021.03.19
【コラム】薬剤部より~漢方彩々 2021年 春号~
暖かな陽気に桜の開花も進み、春の気配がそこかしこに感じられるようになりました。厳しい冬を乗り越え陽春に手が届いた方も、まだ少し風の冷たさに震えておられる方も、さまざまな想いを抱えてこの春を迎えられることと思います。 …続きを読む2021.01.21
栄養課からのお知らせ
当院では、治療食を提供しながら薬膳も、提供させて頂いています。 今回、薬膳について皆様方にしってもらえたらいいなあと思い掲載させて頂きました。 一緒に薬膳料理を楽しみましょう!! …続きを読む2020.12.01
【コラム】薬剤部より ~漢方彩々 2020年 冬号~
2020年も残すところ1ヶ月、年末に向けて空気がぴりっと乾燥し、風邪などの感染症が流行し始める季節になりました。 今年は特に、今なお不自由な生活を強いられている方も少なくないかと存じます。 苦難の中にも皆さまお…続きを読む2020.10.19
鍼灸『秋の過ごし方』
秋気が肌にしみる季節となり、肌寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。 秋は、残暑による夏バテに加えて、朝夕の寒暖差や、空気の乾燥などによって、呼吸器系・皮膚症状などが現れやすい季節でもあります…続きを読む2020.01.31