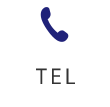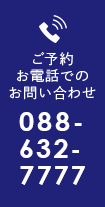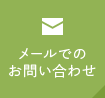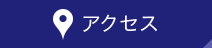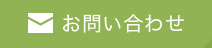「やさしい満足感:豚かつの卵とじで整える一日の力」
やさしい味付けと彩りのバランスが、目にも心にも食欲を運んでくれます。病院食というと「味気ない」という印象を持たれがちですが、当院の献立は家庭的な温かみと栄養バランスの両方が整った一食です。
このお食事は隣接するサービス付き高齢者向け住宅、ショートステイやデイケアでも提供されています。入院中の方だけでなく、在宅生活を送る高齢者や通所利用者様も、同じ美味しさと健康サポートを受けられるのです。
① 「だしの香りに包まれる一膳」
本日のメインは、やわらかい豚かつを出汁で煮含め、玉ねぎと卵でふんわりとじた「豚かつの卵とじ」です。つややかなご飯、青菜と豆腐が香る味噌汁、コクのある「切り干し大根のマヨネーズ和え」、そして彩りのよいデザート(果物ゼリー)を添えました。揚げ物でも出汁と卵でやさしく仕上げ、食べやすさと満足感の両立をねらっています。

② 「からだに灯る、やさしい栄養のひかり」
この一膳で、主食・主菜・副菜・果物がそろいます。エネルギーと栄養のバランスがとれた献立です。
- ・豚肉(豚かつ):ビタミンB1が多く、ご飯の糖質をエネルギーに変える助けをします。だるさ対策にも役立ちます。
- ・卵:良質なたんぱく質で筋力維持をサポート。さらにビタミンDを1個あたり約2.2μg含みます。
- ・味噌汁:発酵食品のうま味が食欲を助け、体をやさしく温めます(塩分はとり過ぎに注意)。
- ・切り干し大根のマヨ和え:食物繊維・カルシウム・鉄がぎゅっと凝縮。少量の油は脂溶性ビタミンの吸収を高めます。
- ・デザート(果物ゼリー):ビタミンCと水分の補給に。
ビタミンDのとり方
- ・成人の目安量は1日8.5~9.0μg。
- ・卵1~2個で3~4μg=目安量の約半分弱をまかなえます。
- ・残りは魚(鮭・イワシ・サンマ)やきのこ、そして適度な日光で補いましょう。
- ・卵だけで満たそうとすると4個前後必要になります。いろいろな食品を組み合わせるのが現実的で安全です。
骨と筋力を守るポイント
- ・ビタミンDは腸でのカルシウム吸収を高めるため、骨密度の維持と骨折予防に役立ちます。
- ・不足すると骨がもろくなり、骨粗鬆症のリスクが上がります。
- ・十分にとると骨密度の低下を抑え、転倒予防(筋力維持)にもつながります。
- ・病状によっては活性型ビタミンD製剤が使われることがあります(医師の管理下で行います)。
骨粗鬆症は加齢や閉経後のホルモン低下が主な原因ですが、カルシウムとビタミンDの不足も関係します。毎日の食事と少しの外歩き(日陰や朝夕の時間帯でも可)を習慣にしましょう。
※本記事は一般的な健康情報です。持病のある方、薬を飲んでいる方は、量や食材の選び方について必要に応じて主治医にご相談ください。
③ 「季節をいたわる、小さな養生の知恵」
季節の寒暖差は、胃腸(いちょう)の働きをゆらしがちです。 今日の献立は、だしの香りと卵のやわらかさでお腹にやさしく、味噌が体の中心をほどよく温めてくれます。豚肉は体のうるおいを補い、乾きがちな粘膜のケアにも向くとされます。 ※以下は東洋医学の考え方をわかりやすく示した比喩的な説明です。医学的な診断・治療の代わりにはなりません。
東洋医学のポイント
- ・「腎(じん)」を助ける食材=豚肉 東洋医学・薬膳では、豚肉は「補腎(ほじん)」といって、からだの基礎力を支える食材とされています。
- ・「腎」は広い概念 現代医学の腎臓そのものだけでなく、泌尿・生殖のはたらき、骨・耳・髪の健康、体力の土台などを含む広い考え方です。
- ・「腎虚(じんきょ)」とは? 加齢や疲れなどでこの「腎」の力が弱った状態のこと。次のようなサインが語られます。
- 〇だるさ・疲れやすさ
- 〇足腰の弱り・冷え
- 〇骨や歯の弱り、骨粗しょう症の心配
- 〇聴こえにくさ、耳鳴り
- 〇髪が細くなる・抜けやすい
- 〇トイレが近い、夜間の排尿
- 〇皮膚の乾燥、むくみ など
- ・食養生の考え方 豚肉は日常に取り入れやすい「補腎」食材のひとつ。無理のない量で、穀類・野菜・魚と組み合わせ、温かい汁物を添える――そんなシンプルな食べ方が、季節の揺らぎに寄りそいます。
東洋医学の知恵は体調のヒントになりますが、治療そのものではありません。体調不良が続く、骨や転倒の不安が大きい、排尿や栄養で心配がある――そんな時は、自己判断をせず主治医にご相談ください。食材だけで治そうとせず、栄養・運動・睡眠・服薬をバランスよく整えることが大切です。
④「ゆっくり、やわらかく—安心のひと工夫」
豚かつは食べやすい大きさにカットし、だしでしっとり。味噌汁はほどよい温度で誤嚥を予防します。切り干し大根はよく噛んで水分も一緒に。むせやすい方はお茶やスープで“しっとりのど”を意識しましょう。持病やお薬のある方、食事量が進みにくい日は、無理せず量や硬さを調整し、必要に応じて主治医にご相談ください。
⑤ 「今日のあたたかさを、明日の力に」
季節の揺らぎに負けないよう、今日も一膳で体の芯から温まっていきましょう。皆さまの健やかな日々を心よりお祈りします。
【注釈】
各個人様にお出しするお食事は、体の状態や医師の指示により内容が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の診断・治療に代わるものではありません。症状や治療については必ず主治医にご相談ください。