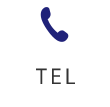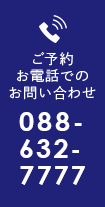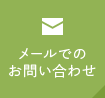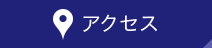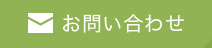ふっくらうなぎと五穀の力:心も体も温まる病院食
やさしい味付けと彩りのバランスが、目にも心にも食欲を運んでくれます。病院食というと「味気ない」という印象を持たれがちですが、当院の献立は家庭的な温かみと栄養バランスの両方が整った一食です。
このお食事は隣接するサービス付き高齢者向け住宅、ショートステイやデイケアでも提供されています。入院中の方だけでなく、在宅生活を送る高齢者や通所利用者様も、同じ美味しさと健康サポートを受けられるのです。
- ①小さなご馳走、今日のならびをご案内
本日の献立をご紹介します。主食は、ぷちぷちとした食感が楽しめる五穀ご飯です。白いご飯に比べて香ばしさがあり、かむほどに味わいが出ます。主菜には、香ばしく焼いたうなぎの蒲焼きをご用意しました。食べやすいように一口大にして添えています。れんこんやにんじんをいっしょに盛りつけ、色どりを明るくしました。汁物は、澄んだ出汁のすまし汁です。大根や青菜をやわらかく火を通し、素材そのもののうまみを生かしています。副菜にはクリームシチューがあります。鶏肉、にんじん、ほうれん草などの具材を、牛乳のまろやかなコクでやさしくまとめています。食後にはデザートを小さめのカップでお出しします。ほどよい甘さで、食後のひと息をゆったりと楽しんでいただけるように工夫しています。

- ②からだ想いの、小さな栄養手紙
今日の献立は、毎日の体を支える内容です。五穀ご飯は白いご飯より食物繊維やマグネシウム、ビタミンB群が多めにふくまれます。お腹の調子をととのえ、食後の血糖の上がり方をゆるやかにします。主菜のうなぎには、良質なたんぱく質のほか、DHAやEPAという魚の油、ビタミンA・D・E・B1などがふくまれます。皮ふや粘膜を守り、疲れの回復を助けるはたらきがあると考えられています。シチューの牛乳はカルシウムの補給になり、鶏肉といっしょにとることで骨や筋力を保ちます。すまし汁は水分と電解質(体の水分バランスに必要な塩分やミネラル)を補い、全体の塩分も控えめです。DHAとEPAは体の中ではほとんど作れない大切な油で、特に青魚に多い成分です。DHAは脳や目の材料となり、考える力や見え方を保つとされます。EPAは血液をさらさらに保ち、中性脂肪を下げる作用が報告されています。これらの油は、もの忘れや動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中など血管の病気を防ぐ方向の可能性も示されています。ただし、人によって効果に差があり、大きな差がみとめられないという研究もあり、結論には幅があります。それでも、中性脂肪を下げることや体の炎症をおさえるなど、体を守る方向の作用そのものは多くの研究で支持されています。魚や牛乳、肉や野菜を無理のない量でバランスよくとることが、脳と血管の健康を守る基本です。ここでお伝えした内容は一般的なお話です。食べにくい、制限食があるなど気になる点は主治医にご相談ください。
- ③巡る季節と東洋のまなざし
東洋医学の考え方では、うなぎのようにコクのある魚は「気と血を養う食べもの」とされます。ここでいう気と血とは、体を動かす元気と、体をめぐる血のことを指すと考えられています。夏は暑さでだるくなったり、食欲がおちたりしがちです。そのような時期の疲れやだるさに向く食材とされています。五穀は消化を支えるはたらきがあるとされ、弱った胃腸を助けるイメージです。あたたかいシチューはお腹を冷やさず、体のめぐりをととのえるイメージにもつながります。昔から「土用の時期には“う”のつく食べものをとるとよい」と言われてきました。これは季節を元気に乗り切るための工夫として親しまれてきた養生法です。
この「“う”のつくものを食べる」という習わしには、いくつかの歴史的な背景があります。奈良時代の歌集『万葉集』には、大伴家持が「夏にやせた時には、うなぎをとって食べるとよい」といった内容の歌を残しており、すでに当時から、うなぎが夏の力になる食べものとして意識されていたことがわかります。のちの時代には、「丑の日に“う”のつくものを食べると夏バテしない」という考え方が広がりました。ここでいう“う”のつくものは、うなぎだけではなく、梅干しや瓜、うどん、牛肉や兎の肉など、いろいろな食べものがふくまれていたと言われています。やがてうなぎのイメージがとくに強く残るようになりました。江戸時代のなかごろには、発明家であり蘭学者でもあった平賀源内が、「本日、土用丑の日」と書いた張り紙でうなぎ屋を手伝い、大人気になったという話が伝わっています。この話が全国に広まって、今の「土用の丑の日=うなぎ」という形が定着したというのが一般的な説明です。ただし、この平賀源内の話は通説であり、当時の一次資料にそのまま書かれているわけではないともされています。
奈良時代の『万葉集』という古い資料に、夏にうなぎをすすめる歌が残っていることは事実として確認できます。その後の時代には、「丑の日に“う”のつくものを食べると夏に負けない」という民間の養生法が広がり、その代表として、うなぎが特に知られるようになったと考えられます。昔ながらの工夫には、今の私たちにも参考になる部分があると思います。ただし、食べものの合う・合わない、持病やお薬との関係には個人差があります。気になる点は主治医にご相談ください。
- ④ゆっくり、あなたの歩みに寄り添って
うなぎはやわらかく調理し、きざんだり、小さめの一口大にしたりして、のみ込みやすい形にしています。食事といっしょにとる水分も大切です。すまし汁やお茶などで、こまめに口にしていただくと安心です。食欲があまりない日もあると思います。そういう日は、シチューの具など食べやすいものを中心に、少量ずつでも十分な場合がありますので、無理をせずゆっくり召し上がってください。ただし、腎臓や肝臓のご病気がある方、コレステロールや中性脂肪などの値に注意が必要な方は、塩分や脂質のとり方に気をつける必要がある場合があります。うなぎのタレの量や、どれくらい食べてよいかなど、いつもの主治医や管理栄養士とご相談ください。目安にはなりますが、食べる量や味つけの調整は、その方の体調によって異なります。
- ⑤終わりに
私は本日のデザートの「りんごのコンポート(りんごをシロップでやわらかく煮たもの)」がとても好きです。やさしい甘さで、口当たりもやわらかく、ご高齢の方にも楽しんでいただきやすい一品だと思っています。
季節の変わり目は、体がゆらぎやすい時期です。しっかり食べて、しっかり休むことが、いちばん身近で大切な養生になります。皆さまが毎日を気持ちよく過ごせますよう、心よりお祈りしております。なお、体調に不安がある場合や、食事について気になる点がある場合は、必要に応じて主治医にご相談ください。
【注釈】
各個人様にお出しするお食事は、体の状態や医師の指示により内容が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の診断・治療に代わるものではありません。症状や治療については必ず主治医にご相談ください。